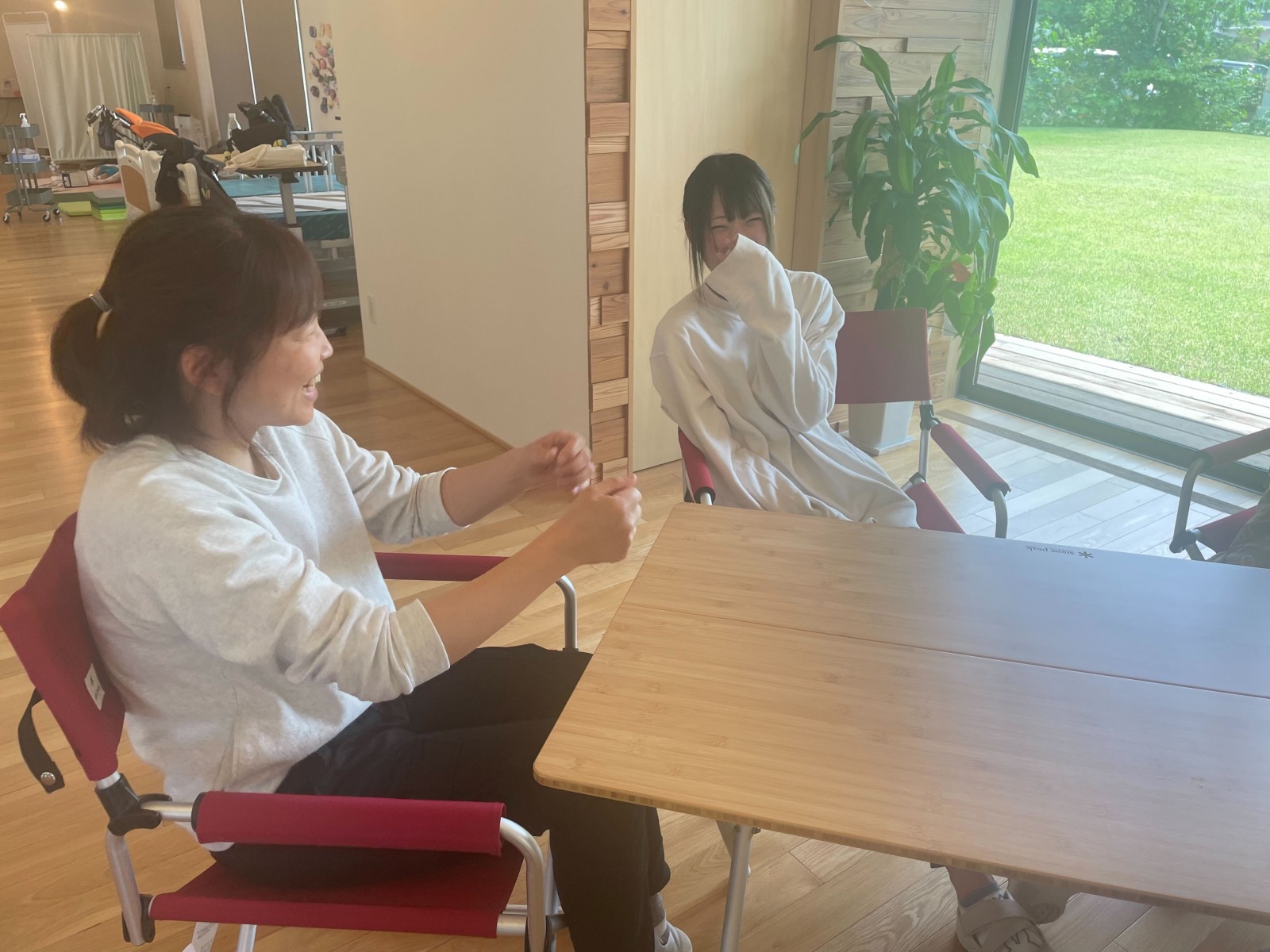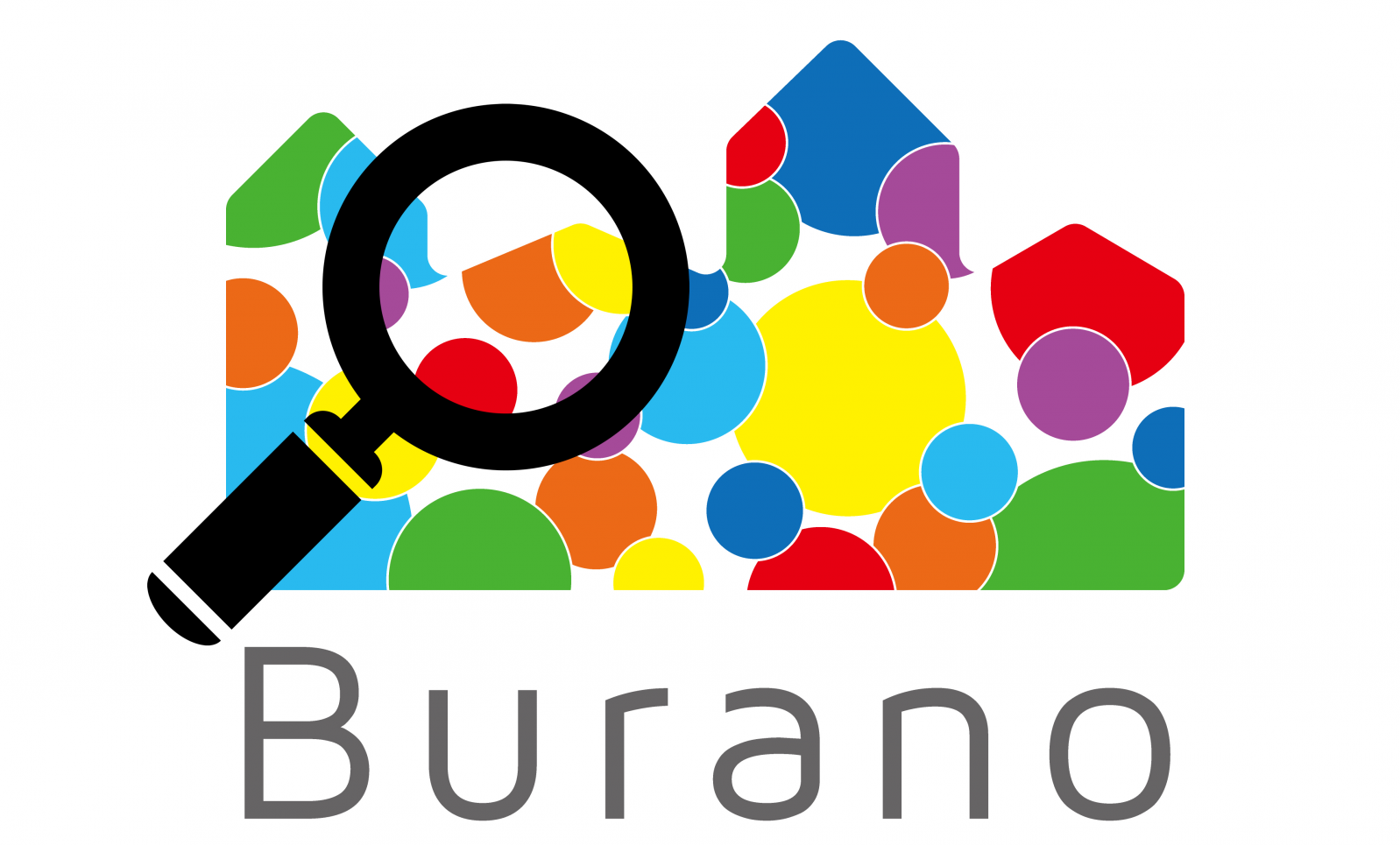kikka

2025.02.18
我が子が病気でも、障がい児でも、私は働きたい。
生まれた直後の我が子の写真を見ると、体はチアノーゼが強く出て青紫色だった。
私の娘には左心室低形成症候群という心臓病がある。
左心室低形成は心臓の左心室が小さく、酸素を多く含む血液を心臓から肺や体に血液を送り出す力がとても弱い重度の疾患である。
健康な人でいうと常に酸欠に近い状態で生活しており、生まれてからずっと酸素吸入が欠かせない。
娘は生後2日で大学病院へ搬送された。
数日後に再会した娘は多くのチューブに繋がれ、麻酔で眠っていた。
その姿はとても衝撃的で、今でも決して忘れられない。

(▲搬送後、ようやく会えた時の娘)
妊娠するまで、歯科衛生士として働いていた。
出産後も復職して働くつもりでいた。
当時は新型コロナウイルスが流行り始めた時期。
“在宅ワーク”という働き方が広まってきた。
「今の自分の状況で家でできる仕事はないだろうか」と考え始めた頃、重度障がい児預かりサービスのBuranoでスタッフとして働く姉からkikkaの存在について教えてもらった。
kikkaは育児と家事を両立させながら、時間や場所の制約にとらわれない「クラウドソーシング」という働き方の支援をしている。
「今の私が仕事をするならここしかない」と思った。
だが、不安はいくつかあった。
まずは自分のパソコンスキル不足だ。
これまで歯科医院で働いていたが、パソコンを使う業務はあまりしていない。
それに仕事を始めたとして作業する時間はとれるのだろうか、作業を優先するあまり娘に影響が出てしまわないだろうか、なども思った。
それでも一歩前に踏み出せたのは、自分という存在を残したかったからだ。
娘が生まれてからずっと、がむしゃらに突っ走ってきた。
その時の私は病気を持つ子どもの母親としては存在していたが、ふとした時に「これまでの自分」ではなく社会とは別のところにいるように感じてならなかった。
これは子育てが始まったばかりの世の親たちがよく感じることかもしれない。
新型コロナウイルスの影響で、様々な交流会やイベントが軒並み中止。それまで行われてきた病気の子どもをもつ親の交流会なども取りやめになり、病気が判明してから何かにすがりたかった私はとにかく孤独感でいっぱいだった。
そんな時にkikkaの説明をするということでBuranoの秋山さんに会うことになった。
パソコンのスキルアップ方法も教えてくれ、今後どんな仕事を任せたいか、お給料の面でもどうやれば効率良く稼げるのか、より具体的な話をしてくれた。
その後も秋山さんは、娘のことについて「うん、うん」「よくここまで頑張ってきたね」と話を聞いてくれた。久しぶりに家族以外の誰かと話せたことが、何よりも嬉しかった。
当事者家族同士だからこそ、病院や行政の手続きの難しさ、子どもの成長と治療に関する不安などを分かち合うことができ、気持ちが軽くなった。
話を終えた私は、kikkaの一員になれたようでとても嬉しかった。
自宅に戻った私は早速パソコンに向かい、眉をしかめながらひたすら作業に取り組んだ。
作業管理シートに自分の名前を残せた時の達成感はなんともいえないほど、心が満たされた。

(▲長いPICU(小児集中治療室)生活にも慣れ、身の回りのものでイタズラをするようになった頃)
kikkaに入ってからは文字起こし業務が中心だった。
今は全国重症児者デイサービス・ネットワーク(=重症児デイサービス事業所支援団体)の事務局でメールチェックや会員様へご案内などの業務をしている。
家事や子どものケア、外来や送迎などの日常の隙間時間に自宅で作業をしている。
どこにいてもパソコンがあれば自分のペースで作業を進めることができ、子どもの体調や家庭事情を考慮して交代やお休みもできる。
連絡のやり取りもチャットで完結できるため、とても助かっている。
娘が退院して在宅になり、息子が生まれた。
息子が保育園に通い始め、いざ新たなスタート!というタイミングでまさかの事態が起きた。
息子が熱性痙攣で搬送、娘も急変により搬送。幸いそれぞれ大事には至らなかったが、事は重なるものだ。
その当時は引っ越したばかりで知人がいなかった。双方の親も遠方にいたため、周りに頼れる人がおらず、自分たちだけで何とか乗り越えるしかなかった。
必然的に時間も気力も労力も全く足りず、仕事にまで手が回らなくなってしまった。
kikkaで同じチームのメンバーに状況を相談したところ、「シフトの交代ではなくしばらくお休みにしましょう」「ママが元気で笑顔でいることが一番!ご自分を大切にしてくださいね」と、休みの提案と温かいメッセージまでくれた。
ほぼ毎日子どもたちと家の中で過ごしており、辛くても吐き出す先がなく心が折れそうだった私をその言葉が救ってくれた。
それまで子どもたちのお昼寝の時間や、夫が帰ってきてからの作業は“仕事”だと思っていた。けれど今は“母親以外のもう一人の自分”と感じている。
仕事に対する不安は今も少しはあるが「辛い時や厳しい状況の時には助けてくれるメンバーがいる」と思えるから、ずっと頑張れている。
だから、これからもこの仕事を続けていきたい。

(▲引っ越してから初めての外来の日。桜が綺麗でぽかぽか日和だった)
今の目標は「長期間一緒に帰省して、その時に娘がBuranoに通う」ことだ。
私が住む地域では娘が通えるデイサービスがほとんどない。
障がいを持つ子や医療的ケアが必要な子と親が離れて、お互いに自立して過ごすという考えがまだ定着していないことも要因の一つとしてあるが、娘の状態が一番の理由だ。
娘は現在、常時酸素吸入と胃ろう(=胃に穴を開けて直接栄養を入れる方法)の医療的ケアを必要としている。
話す事はできないが、ハンドサインや喃語での意思の疎通はできる。何かにつかまりながら自力で起きたり座ったり、ハイハイも少しできる。
このような自力で少しでも動ける状態では、制度的に重度心身障がい児を中心としたデイサービスは利用できない。
私の娘は身体的・精神的・知的に重度の障がい児には該当しない“動ける医療的ケア児”なのだ。
ずっと娘と一緒に過ごしてきた私にとって、一人の人間として過ごせることは自分をリセットできる大切な時間。
しかし、その時間の確保がなかなか難しい。
障がい児も預かってくれるBuranoに行ったら、新しいお友だちやスタッフさんとの交流、これまで知らなかった遊びなどを経験して、外の世界をもっと知ってもらいたい。
「いつでもおいで」と声をかけてくれているBuranoの皆さんに娘をとにかく会わせたい!
もはや「ディズニーに連れて行きたい!」と同じレベルで連れて行きたい(笑)

(▲最近の娘。イベントの撮影スポットにて)
こうやって前向きに進めたのも、病気が分かってから制度的なこと・福祉・保険についてなど、当事者家族だから知っている情報を教えてくれたBurano・kikkaの皆さんがいたからだ。
Buranoと出会えて、
一歩踏み出したから、今の私がいる。
他の誰かと繋がったから、今の私がいる。
今の自分を見つけられて良かった。